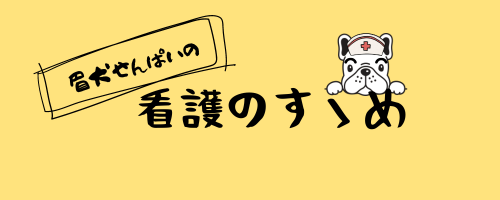看護学生のみなさま、こんにちは!眉犬先輩と申します。
看護師歴約15年、実習担当の指導者に就いた回数は数知れず、自身の実習はするりと切り抜けた私が学校では教えてくれない実習を切り抜けるコツを伝授しますよー
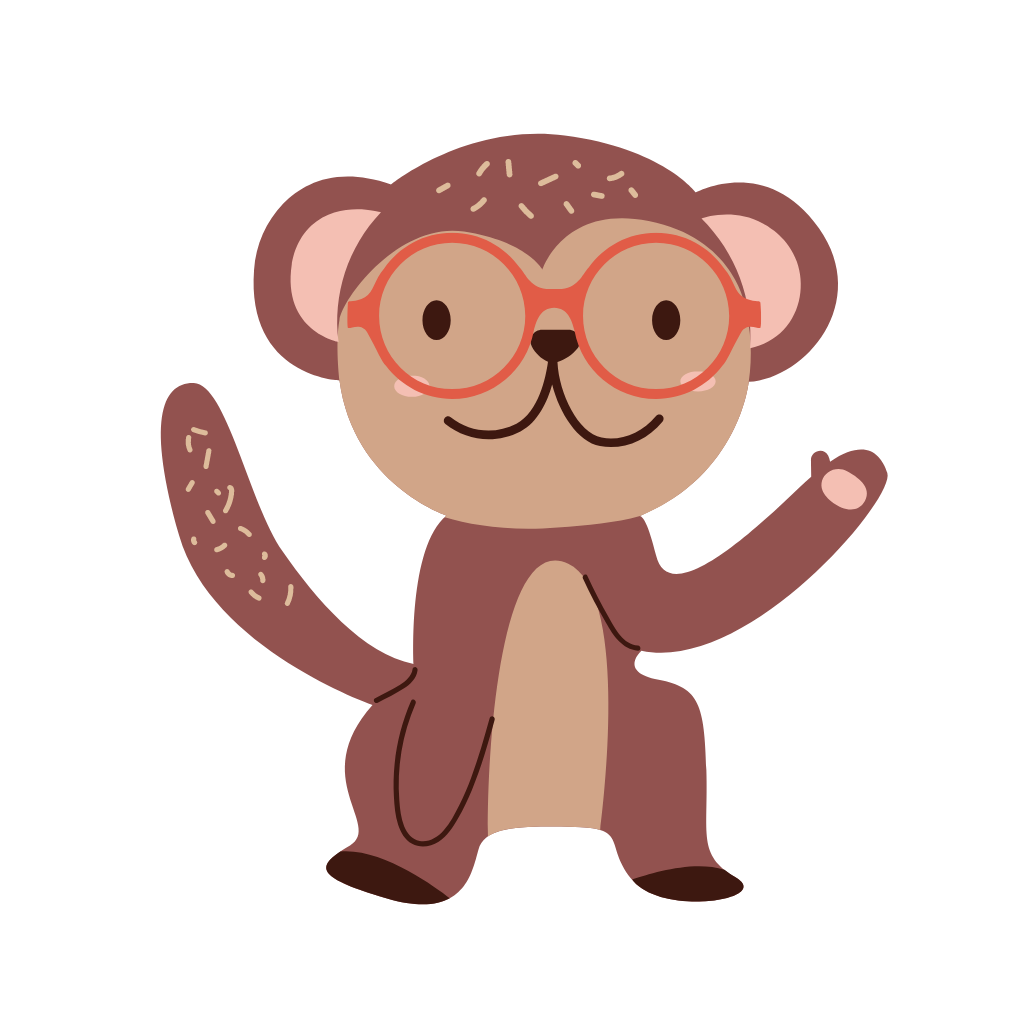
とはいえ、お勉強の方ではなくマナー的な
お話になります。
「なーんだ」と思ったそこの学生さん!
あなどるなかれ、されどマナーなのです!
社会で上手に立ち回る人は、マナーも
きちんとしているものです。

この記事で緊張が取れて、少しでも実習を実りある結果に
して頂けたら嬉しいです。
ではいってみましょう。
実習の挨拶は元気にハキハキと

はい、当たり前のこと~と思いましたね。
何ごとも挨拶は基本中の基本。元気な挨拶は初々しさとやる気が感じられて好印象になるもの。
実習生が病棟に挨拶に来る時間は大体9時前後。
現場は申し送りが終わって、看護師は出動準備を開始している、いわばサーキットのスタート地点のような状態なのです。
現場の雰囲気に気後れしてモゴモゴと挨拶をしていると、指導者に気づかれない事もあり、出発してしまった指導者を探すため病棟を漂流する羽目になりかねません。
また、大きい声すぎてもいけません。
病棟の場合、体調の悪い患者さんや安静が必要な患者さんはナースステーションから近い『ハイケア』というお部屋で休まれていたり、ご家族が付き添っている場合がありますので、声が大きすぎるとびっくりしてしまいます。
帰りや休憩の挨拶も、気付かないほどサラッと言って居なくなると、指導者側は学生さんが居ない!迷子?休憩?と気をもんでしまいますし、印象が良くないですよね。
「挨拶は相手に届かなければ、していないのと一緒」これは、私が尊敬する部長がよく言っていた事なのですが、その通りだと思います。
実習の行き帰りの服装には気を付けよう
大学などでは私服で学校に行くのが当たり前ですし、学校帰りにどこかによる想定でちょっとおしゃれな服を着て行く。これは全く問題ないと思いますよ。しかし!実習先は患者さんや、そのご家族の目があります。
見せるインナーを着ていたとしても、トップスがやけに短くてインナーが見え隠れするような服装や、ダンサーさん?と思うようなダボついた服、ド派手なカラーコーデやダメージジーンズなどは病院には向かないでしょう。
病院にいらっしゃる患者さんは、年齢層も常識もさまざまです。
心がけるべきは誰が見ても不快にならない普通の服装や、オフィスカジュアルがベター。
眉犬先輩が学生の時代は、暗めの色のテーパードパンツにパーカーやトレーナー、カーディガンなどをあわせていました。
実習の行き帰りはリクルートスーツと指定されていれば、その方が楽なのですが眉犬先輩の学校は指定がありませんでした。
なので、このテーパードパンツ2本と手持ちの地味めの服で乗り切りました。
同級生の中には、ダメージデニムにノースリーブを着てきた強者が居て、教員の先生にこっぴどく叱られた挙句、現場の看護師さん達からもクレームが入ったという黒歴史をつくった伝説の子もいました。
みなさんは、そんな心配ないですよね?
服に関連して言えば、靴も重要ですよ。
学生は階段を使うように言われているかと思いますが、ヒールの高い靴や踵がないサンダルのような形状の場合、病院の階段の構造によっては、かなり響きます。
え?!そんな事まで?!細かっ!と思いましたよね?
健康で動き回っている人は気にならなくても、痛みや吐き気で苦しんでいる人には、あの『コツコツ・パタパタ』という音が強烈に響くそうなんですよ。
事実、眉犬先輩の同級生の黒歴史ちゃん、なんと実習にミュールを履いてきましたよ。地上10階の吹き抜けの階段で、盛大に「カン!カン!」とミュールのヒールを鳴らして降りた結果、階段近くの病室から苦情が出ただけでなく病棟から看護師がすっ飛んで来て「学生さん!ヒールの音!静かに!」と遂に直接お叱りを受けていました。
病院は患者さん優先、治療の場であり療養の場ですからね。
安静を阻害するような事を、勉強させてもらっている立場の学生がしてはいけませんよね。
指定が無ければ、足元はスニーカーが良いでしょう。
くれぐれも、厚底やネオンカラーのようなファッショナブルな物ではなく一般的なものをおすすめします。
髪色は黒か自然な茶色で
髪色については、ここでとり上げるまでもなく学校で検査されると思いますが念のため。
校則に違反しない程度に学生の時しかできないカラーを楽しんでるのは眉犬先輩も大賛成です。
近くの医療系大学の前を通るたび、最近の学生さんはオシャレで個性があるな~と思っていますよ。
ただ、実習期間中はカラーを変えましょう。
現場の看護師やドクターからの評価ダダ下がりです。
確かに多様性の時代、海外には金髪の看護師も居ればブロンドの人も居ます。
しかしあなたが向き合う患者さんは、外国の方ですか?恐らく大多数は日本人の高齢者の方です。
あなたが苦しみの末にたどり着いた病院で、出迎えた看護師の頭がピンクやブルー、金髪だったらどうでしょう?
何だか軽そう。怖そう。ちゃんとケアしてくれるだろうか?と心配になりませんか?
眉犬先輩が学生の頃、先輩で明るい茶色の髪色の学生がいました。
たまたま受け持った患者さんが、幼少期に戦争の時代を生き抜いてきた人だったらしく「あの人、日本人なの?優しいんだけど外国の人みたいで怖いの」と担当を外された人が居たそうです。
患者さんからの評価は良かったのに、たった髪色だけで受け持ちをはずされたのです。
多様性とはいえ、医療現場で出会う患者さんの年齢によっては幼少期のトラウマを思い出させてしまう場合がありますので、自身の元の髪色に近いカラーで実習に臨みましょうね。
アクセサリーと爪

こちらも言うまでもありませんが、アクセサリーは現場の看護師でも、結婚指輪以外は認められていない所がほとんどです。
ピアスは、万が一患者さんのベッドに落ちて気付かなかった場合には患者さんを傷つけてしまいますし、認知症の患者さんの場合は食べてしまう事だって考えられます。ネックレスも、かがむ事が多い看護業務では白衣から出て何かに引っかかってしまう事があります。医療機器や患者さんの体に入っているチューブなどに引っかかってしまった場合、重大なインシデントになりかねません。
ピアスホール開けたばっかりなのにー!という人も居るでしょう。
あの半透明なピアスも落ちない保証はありませんし、患者さんの体を傷つけてしまったら責任問題になりかねないのです。
実習時間の数時間であれば、外してもそうそう塞がるものでもないでしょうし、何より実習前にピアスホールを開けるのは避けた方がベター。
装飾品は自分のモチベーションを上げて、指や耳元をきれいに見せてくれる素敵なアイテムです。
眉犬先輩もプライベートではリング4~5個、ネックレスは2連、ブレスレットにピアスはマストですが、仕事の時は生まれたままの耳と指と首元ですよ。みなさんも、実習場ではなくぜひプライベートで美を追求してください。
装飾品と並んで問題になりがちなのがネイルです。
当然カラーをのせてくる学生さんは、今のところお見かけした事はありませんが、長さが問題なのです。
結論から言えば、手のひら側から見て爪が見えない長さが良いですね。
爪は菌の温床になります。現場でも年に何度か手洗いチェックなるものが実施され、爪の間の洗い残しまでチェックされます。
また、長い爪はただでさえ患者さんを傷つけてしまう可能性があるのに割れやすく、ささくれがたちやすくもなります。
高齢の患者さんや新生児の皮膚は薄くて傷つきやすいのです。
自分の爪で傷つけたり、菌を媒介しないように短く切ってよく洗いましょう。
実習中は興味を持った態度で臨みましょう

みなさんご存じ、実習は現地で学ぶ機会です。
患者さんと触れ合い、コミュニケーションをとり、看護問題を見つけて解決する方法を学ぶのです。
何が言いたいかって言うと、多少お勉強が足りなくても許容範囲ってこと。
学生に高い知識や技術を求めている訳ではない。座学で学べる事は学校で学べば良いし、実習で足りないと感じた知識はその場で調べるか帰ってから学べば良いのです。
気付けた事がすばらしいと眉犬先輩は思いますね。
関連図だって、これは・・・?というところは突っ込んで修正してもらいますが、重箱の隅をつつくような突っ込みをするほど現場の看護師も暇ではありません。
実習では、生の体験の中から患者さんの訴えを聞く事ができて治療の流れを見ることができる機会です。
目で見て体験した事は、しっかり記憶に残りますよ。
しかし!興味を持って臨まなければ、当然記憶には残りません。せっかくみなさんを受け入れてくださった患者さんに申し訳ないですし、何より将来必ず現場に出て同じ経験をするだろうに、何も得るものがないまま終わってしまいますよ。
そこで眉犬先輩からのアドバイスです!
実習では、なぜ?を大切に考えましょう。
例えば患者さんが食事の不満を訴えている。これはなぜなんだろう?制限食のためか、味覚そのものなのか、脳の異常なのか、形態なのか。
患者さんとコミュニケーションを取って、カルテから情報を取り、それでも解決しなければ指導者に投げかけてみましょう。
受け持ち患者さんが、なかなかリハビリに乗り気じゃない、もしくは拒否している。なぜだろう?
動かすことで傷みが増すのか、自身の病気を受容できていないのか、どうせと投げやりになっているのか、今日のタイミングの問題か、認知症による気分のむらなのか。
または、なぜこの人にこの検査が必要なのか?など興味を持つ事で考えられる看護問題は山のように出てきますし、おのずと観察するべき項目やコミュニケーションの方向性が見つかりますよね。
実習をうまく進めるアドバイスその2は、自主的に学ぶ事です。
学校とは違い実習では自分はこれが見たい、ここについて知りたい。と主張しなければ指導者的には分かりません。
指導者側としては検査などのイベントがあれば声をかけるけど、他に見たいのは何かな?見学しなくていいのかな?くらいです。
気付いた時には見たい処置やカンファレンスは終わっていることだってあり得ます。
あらかじめ言ってもらえると、指導者も時間の調整をして検査の説明をしたりカンファレンスの概要やテーマについて説明する事だってできます。
指導者的にも、あの学生さん何も言って来ないで、ただ患者さんにくっついて歩いてるだけだけど大丈夫かな?いいのかな?とモヤモヤしなくて済みます。
実習では、患者さんの生の訴えを聞く事ができますし、座学では知ることのできなかった現場の工夫が見れます。
興味を持ってコミュニケーションをとったり、質問を投げかけて来る学生さんはある程度情報収集もしているので「この患者さんは、食形態がペーストなのに味噌汁にとろみが無いのはなぜですか?」「排便コントロールで浣腸と座薬を使い分ける理由はなぜですか?」「ドレーンがこことここに入っている理由を教科書でここまでは調べられましたが、ちゃんとした理由が分からなかったので教えてください」など、調べたうえで足りない知識を質問する事が多いです。
大した質問ではなくても、自分でも調べたけれど足りない部分があったから教えて欲しいというスタンスが重要なのです。
全く調べもしないで、指導者に質問を投げるのはナンセンスです。指導者によっては怒られる場合も・・・お気をつけくださいね。
実習時間はシャキッとキビキビと動いて周囲に気をつかって
これは眉犬先輩がよく思う事。
学生さんに提供しているスペースは、本来は患者さんが使うスペースなわけです。(学生室が準備してある病院は別です)
しかし、患者さんがそこを使おうが患者指導の準備をしていようがお構いなく座り続けている学生さんをよく見まけますが、これはいけません。
「ちょっとここ使うから、場所をあけてね~」って言えば良いと思いますよね。
最終的には言うのですが、大切なのは察知して自分から「ここ使いますか?」と言って場所を開ける事。
言われる前に自分から申し出る。これが好印象なのです。
この他にも、学生さんが横並びで廊下を歩いていたり、患者さんと歩行練習しているでもない学生が、ゆったりのんびり廊下のど真ん中を1人で歩いている状態。
病院は患者ファーストなんですよ。
患者さんがその場所を使う様子を察知したら、場所をあける。廊下はダラダラ歩かない。まして学生1人なら端による。
角を曲がる時には、向かいから歩いて来る患者さんと正面衝突しないように人が来ないか確認する。
看護師も迅速に検査に出さなければいけない検体を持って、急ぎ足で歩いている事もありますので動線を塞がない。
細かいようですが、見ている人はこういう所みています。
現場の指導者ではない看護師が、急変時に廊下を塞いで歩いていた学生さんに声を荒げた事もありました。
コンプライアンスを重視する時代ですが、急変や緊急時にダラダラと道を塞がれては声を荒げるスタッフも居なくはないのですよ。
急変が無くても、現場の看護師は業務を山ほど抱えていて、時間とのたたかいですのでパタついている事が多いんです。
ゴミ箱は歩きながら一瞬で捨てたいですし、ミキシング台は時間によっては場所の取り合い状態です。
なので、出入り口に留まらない、ごみ箱周辺や点滴のミキシング台の真ん前に立ちはだからないことも細かいようで重要です。
周囲に気を配りながら行動する事を心がければ、きっと回避できるはずですよ。
怖い指導者でも遠慮は無用
現場には厳しい看護師も居ます。患者さんの安全が第一なわけですから、厳しい指導の場面もあります。
ただ性格がサバサバしているだけ、言い方がキツイだけの人もいます。
とはいえ、学生からみれば「ただの怖い指導者」ですよね。
しかし、臆することはありません。謙虚に一生懸命がんばる姿勢を示すのです。
興味を持って質問する、教えてもらったらお礼を言う、翌日に検査があるかどうか確認して事前学習して来る、謙虚な態度、そして提出物は教科書や辞書の丸写しではなく調べて理解した事を書き出す。
ここまでやって怒られた場合、諦めてお叱りを受けましょう。
無責任な!と思うかも知れませんが、現場の指導者の知識や指導内容は十人十色といっても過言ではありません。
もちろん指導要綱は読んでいますが、そこまで細かくは書かれていません。
指導者も人間なので、性格的な問題もあるでしょう。
フォントが合っていない、誤字脱字があるなど校閲か⁉と思うような事で注意する人も居れば、患者さんに対する態度、目線の高さ、手の添え方など態度を細かく見る人も居る。
もちろん、どれも大切な事ではあるのですが、こんな対策を指導者ごとに挙げていったら正直キリがないのです。
叱られた内容に心当たりがあれば、次の実習先では同じことで叱られないように気を付ければ良いですし、理不尽だと思った事は先生に相談してみるのも良いですよ。
経験豊かな先生であれば、実はあなたが理不尽と思っていた事が違う意味合いだった。なんて気付きをもらえるかも知れません。
先生の解釈やアドバイスを受けられるのも学生の特権ではありませんか。
1年目として就職したら、相談するのも怒られるのも先輩なのです。
毎日顔をあわせますし、叱られた内容について自分ががこうだったから?と聞き返したり、解釈を求める事なんてできないでしょう。
注意された内容を自分で考えて、自分で対策を練らなければいけなくなるんです。
むしろ、学生で先生という強力なサポートが居るうちに厳しい指導を受けて、どう理解してどう次回に生かせるか一緒に考えた方が良いと思いませんか?
現場では緊張感を持って
学生といえども、関わっているのは本物の患者さんです。危険の回避や安全確保は必要です。
違う事を考え、一瞬目を離した隙に点滴を目の前で抜かれた、転倒してしまったというような重大事故が発生する事は防がなくてはいけません。
学生に1人で介助させるような現場はあまり無いかと思いますが、歩行が不安定な患者さんに付き添う場合、どう転んでも支えられるように少し斜め後ろか真横につく、抑制を外している患者さんからは目を離さない、車いす移乗などは必ず指導者についてもらう、患者さんが1人で大丈夫と言っても油断は禁物。1人で行動しても大丈夫な患者さんなのか指導者に確認する。歩行が不安定な患者さんが歩き出してしまって、近くに看護師が居ない、でも患者さんから離れられなくてどうして良いか分からない時は勇気をもってナースコールを押しましょう。
「学生の〇〇です。患者さんが歩き出してしまいました」「点滴を引っ張っています」など簡潔に報告して助けを呼びましょう。
まずは自分が考えうる限りの危険回避をして、患者さんを危険にさらさない事は何よりも大切な事です。
自分が同じ行動をしても転ばないでしょ。と思ってもベッドに居る時間が長ければ筋力は落ちますし、術後などは若くてもぼんやりしていたり、せん妄になる事だってあります。
シャキシャキして見える高齢者も判断力が落ちていたり、遠慮して学生を敬遠する事もあります。
実習中は常に緊張感を持って、配慮を心がけましょう。
勝手なアドバイスや自己判断、興味のなさそうな態度での接し方は駄目ですよ。
実習の持ち物
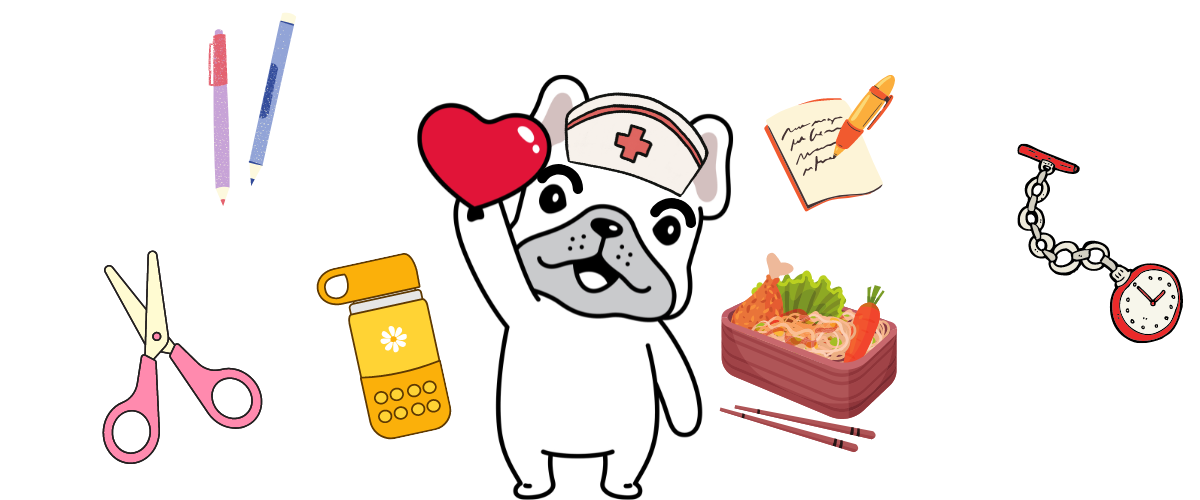
- 3色ペン(できればシャープペン付の4色ペンがおすすめ)
- ポケットサイズのメモ帳
- ポケットに入る秒針付の時計
- ハサミ(あまり使う機会はないけれど、あれば良い)
アドバイス
眉犬先輩が学生の時に心がけた事、実践していた事を書き出しておきますので、良かったら参考にしてみてくださいね。
- 代表で挨拶する時は率先して自分がやる。
- 挨拶、お礼はハッキリ言う。
- いつも笑顔で。
- 爪や白衣の乱れなど最低限の身だしなみでは絶対に注意されないようにする。
- 髪はお団子、シュシュなどのヘアアクセサリーは使わない。
- 記録は理解するまで参考文献を読んで書き出す、図解した方が分かりやすかったら図解する。後から自分が見ても参考になるように簡潔で分かりやすく書く。妥協しない。
- 看護師の邪魔はしない。急いで歩いてきた看護師とすれ違う時は壁に張り付く。
- 患者さんと話をする時は、目線を合わせる。
- コミュニケーションは、まず相手の事を聞き出そうとするのではなく自分の事を話す。患者さん側から話してくれる人なら、聞き役に徹して共感する。
- 自分のせいで患者さんを危険にさらさない。
- 学生同士で話し込まない。確認し合わない。
- 失敗は素直に認めるか、自分から申し出てすぐに謝罪する。お辞儀する時は常に90度。
- 怖い指導者でも聞くべき、確認するべき事は遠慮せず話しかける。
- 看護師に話しかける時は「今、話しかけてもよろしいでしょうか」「お忙しいところ申し訳ありません」をその時々で使い分けて話しかける。
- 注意を受けたら「申し訳ありませんでした。次回から気を付けます」と素直に頭を下げる。
- 質問は簡潔に、タイミングをみて。
- 質問する前に自分で調べる。(この事について自分なりに調べたけれど、この解釈で合っていますか?という具合の質問をする)
- 実習先を出たら、学生同士で情報共有する。(どんな事で注意を受けたか、今日何があったか、指導者からもらったアドバイスなど)
こんなところでしょうか?
下僕じゃないんだから、ここまでやる必要がある?と賛否両論な内容かもしれませんが、私は突っ込まれたくないし何度も注意されるのが嫌だったのでここまでやりました。
なぜならここまでやって、それでもまだ叱られる事があるなら甘んじて受けようと思えるからです。
真似するかどうかはお任せしますが、参考までに。
このお陰か、何人も泣いて帰ってきた超急性期の実習先でも眉犬先輩は比較的指導者さんに優しくしてもらえたと思いますし、実習中に泣いた事はありません。
ちなみに新人の時も泣いたのは「面倒だな~」と思って後回しにした業務が実は緊急度が高くて叱られた時に、自分の甘い判断が引き金になった事が悔しくて泣いた事が1回です。